こんにちは、well-bingです!!大学で福祉を学び、社会福祉士と精神保健福祉士を取得しました。皆さんに少しでも福祉分野に興味・関心を持ってもらったり、この情報によって自分らしい生活を送っていただくために今はブログ活動しています。
この科目では、内容が広範囲で、高齢者の生活課題や介護保険の仕組みを深く理解することが求められ法律や制度の細かい知識も必要なため、苦手意識を持つ受験生も多いと思います。そこで、基礎知識から頻出問題の傾向、効率的な学習方法まで、ポイントを分かりやすく解説します。これを読んで試験対策の道筋が明確になれば幸です!
「高齢者に対する支援と介護保険制度」とは?
科目の概要
「高齢者に対する支援と介護保険制度」では、以下のようなテーマを学びます。
- 高齢者の生活支援:身体的・精神的な特徴、社会的役割の変化
- 介護保険制度:制度の仕組み、サービス内容、財源など
- 家族支援:介護を担う家族の負担軽減策や心理的支援
- 法令や制度の改正:介護保険法や高齢者福祉に関する法律
これらはすべて、高齢者の「生活の質」を高めるための重要な要素です。この科目を学ぶことで、支援者としてどのような知識やスキルが求められるかを理解できます。
2. 介護保険制度の基本情報とポイント
介護保険制度は、この科目の核となる内容です。複雑な仕組みですが、試験において頻出する部分を押さえれば、効率よく得点できます。
介護保険制度の概要
介護保険制度は、2000年に始まった日本の社会保険制度で、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるようにすることを目的としています。
主なポイント
- 保険者:市町村および特別区
- 被保険者
- 第1号被保険者:65歳以上の高齢者
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
- 給付内容
- 居宅サービス(訪問介護、デイサービスなど)
- 施設サービス(特別養護老人ホームなど)
- 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護など)
- 財源構成:保険料(約50%)、公費(約50%)
試験に出やすいトピック
- 要介護認定の手続きや判定基準
- 地域包括ケアシステムの概要
- 改正介護保険法のポイント
具体例で理解を深める
例えば、地域包括ケアシステムでは、医療・介護・生活支援が一体となったサービスを提供します。この「包括的支援」の考え方は試験でもよく問われるテーマです。
図表で解説
介護保険制度の仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 高齢者や障害者が自立した生活を営むための支援を行うための社会保険制度。 |
| 対象者 | 1. 第1号被保険者:65歳以上の人 2. 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
| 保険者 | 市町村および特別区 |
| 財源 | 保険料(第1号・第2号被保険者)、公費(国・都道府県・市町村負担) |
| 利用者負担 | 原則としてサービス利用料の1割~3割(所得に応じて変動) |
介護サービスの種類
| サービス種別 | 具体例 |
|---|---|
| 居宅サービス | 訪問介護、通所介護(デイサービス)、訪問看護など |
| 施設サービス | 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設など |
| 地域密着型サービス | 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など |
| 予防サービス | 要支援者向けの訪問型・通所型サービス |
要介護認定の流れ
A[申請] --> B[認定調査];
B --> C[一次判定];
C --> D[介護認定審査会];
D --> E[認定結果通知];- 申請:市町村窓口で申請
- 認定調査:訪問調査と主治医意見書
- 一次判定:コンピュータによる判定
- 介護認定審査会:専門家が総合的に判断
- 認定結果通知:要支援・要介護度を決定
高齢者への支援の視点
| 視点 | 具体例 |
|---|---|
| 身体的支援 | 食事、入浴、排泄の補助など |
| 心理・社会的支援 | 認知症ケア、孤立防止のための交流支援 |
| 環境整備 | バリアフリー住宅、福祉用具の導入 |
| 権利擁護 | 成年後見制度の活用、虐待防止 |
| 地域社会との連携 | 地域包括支援センターやボランティア活動の活用 |
練習問題
問題1(選択式)
介護保険制度における「要介護認定」の手続きに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 要介護認定の申請は、本人または家族しか行えない。
- 要介護認定の一次判定は、主治医が行う。
- 要介護認定の結果は「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれかに分類される。
- 要介護認定審査会は、都道府県が設置する。
解答:3
解説:
- 誤り:要介護認定の申請は、本人や家族だけでなく、地域包括支援センターやケアマネジャーなど代理人も行うことができます。
- 誤り:一次判定は、認定調査の結果と主治医意見書を基にコンピュータで行います。主治医は一次判定そのものを行うわけではありません。
- 正しい:要介護認定の結果は「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」に分類されます。
- 誤り:要介護認定審査会は、市町村が設置し、保健・医療・福祉の専門家で構成されます。
問題2(正誤問題)
地域包括支援センターに関する次の記述について、正しいものには〇、誤っているものには✕をつけなさい。
- 地域包括支援センターは、主に介護予防ケアマネジメントを担当する機関である。
- 地域包括支援センターは、社会福祉士、保健師、ケアマネジャーが配置されることが義務づけられている。
- 地域包括支援センターの設置は、都道府県が責任を持って行う。
解答:
- 〇
- 〇
- ✕
解説:
- 正しい:地域包括支援センターは、要支援者に対する介護予防ケアマネジメントの役割を担っています。
- 正しい:地域包括支援センターには、社会福祉士、保健師(または経験のある看護師)、主任介護支援専門員の配置が義務づけられています。
- 誤り:地域包括支援センターの設置は、市町村が責任を持って行います。
問題3(事例問題)
Aさん(78歳)は要介護2の認定を受けているが、最近、認知症の症状が進行し、1人での生活が難しくなってきた。娘夫婦が同居を検討しているが、日中は仕事があるため十分な介護ができない。Aさんが自宅で生活を継続するために、最も適切なサービスはどれか、次のうち1つ選びなさい。
- 介護老人保健施設への入所
- 小規模多機能型居宅介護の利用
- 特別養護老人ホームへの入所
- 訪問リハビリテーションの利用
解答:2
解説:
- 誤り:介護老人保健施設は、リハビリを中心とした短期入所が主であり、自宅での生活継続のためには適していません。
- 正しい:小規模多機能型居宅介護は「通い」「訪問」「泊まり」のサービスを組み合わせ、柔軟に在宅生活を支援するため、Aさんのようなケースに適しています。
- 誤り:特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、要介護3以上が原則であり、Aさん(要介護2)は対象外です。
- 誤り:訪問リハビリテーションは、主に機能回復を目的としており、認知症ケアや日常生活支援には不十分です。
過去問から学ぶ重要ポイント
過去問を分析すると、以下のトピックが頻出しています。
- 要介護認定の仕組み
- 要支援と要介護の違い
- 認定の流れ(申請、調査、審査会)
- 介護保険サービスの種類
- 各サービスの特徴と対象者
- 費用負担割合
- 法律や制度の改正
- 改正内容が反映されるケースが多い
過去問を使った学習法
- まずは過去問を解く:3年分を目安に演習します。
- 間違えた問題を徹底分析:解説を読み、関連する知識を確認します。
- 繰り返し復習:苦手な箇所を重点的に復習することで、知識を定着させます。
5. 最後に

社会福祉士国家試験は決して簡単ではありませんが、正しい方法で学習を進めれば必ず道は開けます。「高齢者に対する支援と介護保険制度」は、試験だけでなく実際の現場でも役立つ知識が詰まっています。この科目を深く学ぶことで、支援者としての力を高め、自信を持って高齢者やその家族に寄り添うことができると思います。皆様のご健闘を心よりお祈りしております。少しでも安心して生活できるよう、心から応援しています。今回の情報を活用して、より豊かな生活を送ってくださいね!
参考文献
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」
- 全国社会福祉協議会『社会福祉士国家試験受験ワークブック』
- 試験対策講座資料
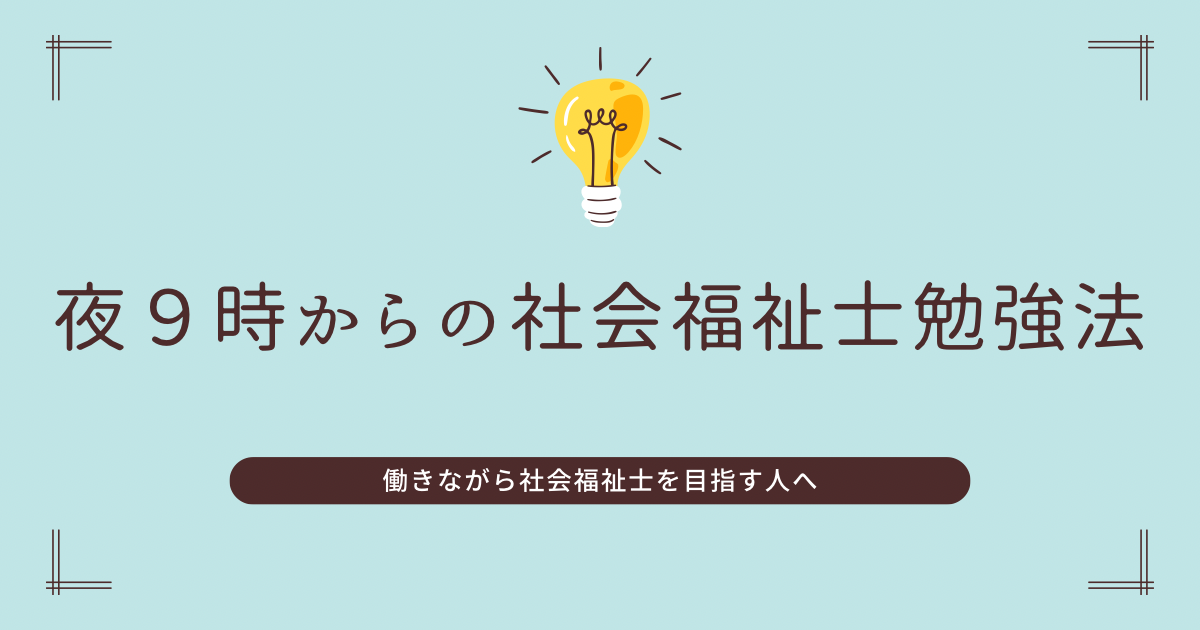
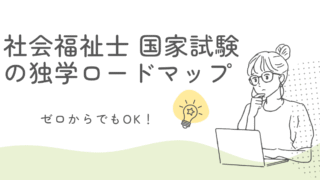
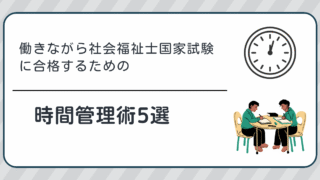
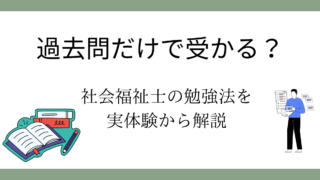

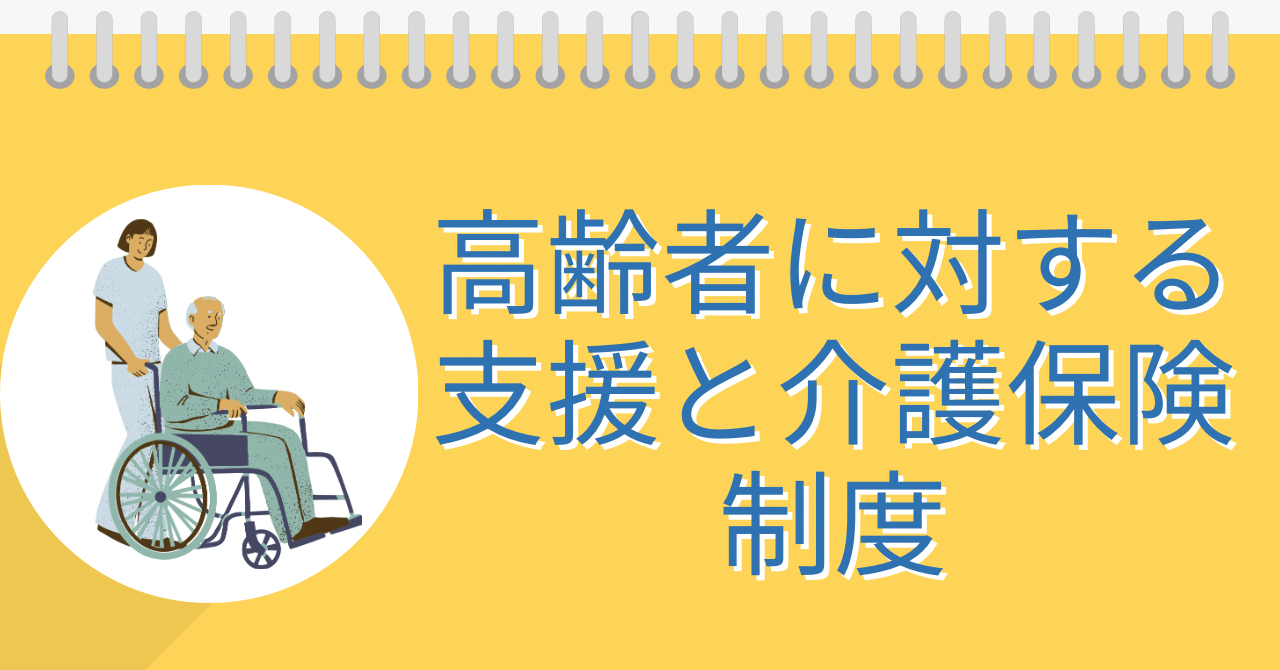


コメント