こんにちは、well-bingです!!大学で福祉を学び、社会福祉士と精神保健福祉士を取得しました。皆さんに少しでも福祉分野に興味・関心を持ってもらったり、この情報によって自分らしい生活を送っていただくために今はブログ活動しています。
試験合格のカギは効率的な勉強法にあり!
この試験は合格率が約30%と、決して高い合格率ではありません。学校を卒業してすぐに受験する新卒受験者の合格率は、平均より高め(50%前後)です。一方、一般受験者や社会人受験者の合格率は低め(20%前後)になる傾向があります。つまり、一般受験者や社会人受験者の方は、しっかりと時間をかければ合格率があがるということです!!
しかし、「そんな時間なんてないから合格できていないんでしょ」と声が聞こえてきそうですね。そこで「どこから手をつければいいのかわからない」「膨大な範囲に圧倒される」そんな不安を解消するヒントをお伝えします!本記事では、私が実際に試験勉強を通じて得たノウハウを、体験談として詳しくご紹介します!
試験勉強のスタート:まずは計画を立てよう!
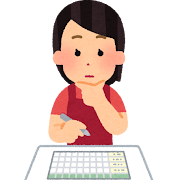
なぜ計画が重要なのか?
自分も受験生の時は、とにかく勉強しなくては!とすぐに勉強に取り掛かり、ただ闇雲に参考書を読んでいましたが、なかなか頭に入らず、焦るばかりでした。しかし社会福祉士国家試験の範囲は非常に広く、すべてを完璧に網羅するのは難しいです。19科目ある上に、絶対に1科目一問以上正解しないといけません。そこでまずは、「どの分野をどの程度学習するか」を簡単に計画することで、効率的に知識を身につけることができます。
※初めに立てた計画は変えてはいけないものではないのでその都度見直していきましょう。
具体的な計画の立て方
以下のステップを参考にしてみてください:
- 試験日から逆算して学習スケジュールを作る
- 例:試験まで6か月の場合、前半4か月で全範囲を一通り学習し、後半2か月で総復習に充てる。
- 優先順位を決める
- 過去問の出題頻度を参考に、「頻出分野」と「苦手分野」に重点を置く。
- 1日の学習時間を細かく割り振る
- 例:午前はテキスト読解、午後は問題演習、夜は復習といった形。
1番効果のあったのは過去問演習の繰り返し
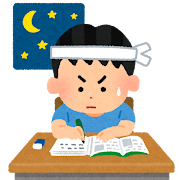
私は試験勉強を始めた当初、インプットを中心に参考書や、教科書を読んでいましたが、眺めているだけで頭に入らないしつまらない。しかも実際に問題を解いてみると全然解けず、何がわからないかもわからない状態でした。この経験から、「問題形式を理解すること」が重要だと気づき、過去問演習に力を入れるようになりました。勉強の始めから過去問を解いていっていいんです!!むしろ解いてください!
過去問をどう使う?
私がやっていたのは、まず4〜6年前の過去問を利用することです。直近3年のものは試験が近くなり実際に試験形式で行いたいというのもあり、始めは、4〜6年前のものから手をつけ始めました。
まずは、20問ずつくらいから解いて答え合わせをするを繰り返す。
実際に過去問を解こうとすると、
- 全て解き切ってから答え合わせ
- 1問ずつ解いて、その都度答えをみる
この二つの方法をやってしまいがちですが、
まず1の場合、過去問を解き切って力尽きてしまう上に、答え合わせで問題を間違えすぎで嫌になります。
2の場合、1問1問に時間をかけすぎてしまい全然進みまず嫌になります。
そこで、20問程度(問題数はお好みで)まとめて解いて、答え合わせをしてくという方法が有効です。それを行うことで、ある程度進むし、問題を覚えているうちに答え合わせができます。また、時間がない時でも、20問だけやろう。とか今日は疲れているから10問ずつにしようと決められます。
過去問の反復方法
大体、一つの過去問を4〜5週程度するイメージでやっていくと良いと思います。人によって試験日までの時間がまちまちだと思うので回数や反復する年度は変わってくると思いますが、基本的には問題を覚えてしまうくらいまではやったほうがいいでしょう。
1週目
一週目に関しては、解説をじっくり読みすぎないこと!!1週目は、問題の聞かれている内容・自分が選んだ選択肢・合っている選択肢を確認するだけで十分です。選択肢1つずつどこが間違っているのかやっていたら挫折してしまいます!こんな感じの問題かということと、正解はこれというのはしっかりと押さえておきましょう。
2週目
今度は解く段階で迷った選択肢、意味がわからなかった選択肢をしっかりと回答を見ながら確認していく。
3週目
基本的には8割〜9割正解できるようにし、一問の中で、全選択肢なんとなく間違えているポイントがわかるように学習していく。
4週目〜5週目
問題もだいぶ覚えてきるので1回20問ずつ解いていたものを、30〜40のように問題数を増やしていく。そして、不正解の選択肢もどこが間違いかわかるように学習していく。
大まかにこのようなイメージで学習を進めていくと自分でも解けるようになっていく感覚が身につき、捗ると思います。解説を読む時や、寝る前や、移動中に参考書を活用するとさらに効果があると思います。
効率的な学習法:繰り返し学ぶ「ザイアンス効果」を活用!
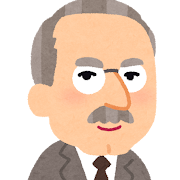
心理学を知っておくことで効果的に学習を進められます。
過去問を繰り返しとけと解説してきましたが、私がたまたまうまくいっただけでしょう?と思う方もいるかもしれません。
ここで参考までに、一つの心理学を紹介します。それが、「ザイアンス効果(単純接触効果)」があります。この心理学の法則を勉強に応用することで、記憶の定着を大幅に高めることが可能になります。
ザイアンス効果(**Zajonc’s Effect**)は、アメリカの社会心理学者ロバート・ザイアンス(Robert Zajonc)が1968年に提唱した理論で、「人は、繰り返し接触する対象に対して、より親近感や好意を抱きやすくなる」という現象です。この効果は、日常の人間関係やマーケティング、学習など、さまざまな分野で確認されています。※ここでは、勉強法メインで話をしたいので興味のある方は是非調べてみてください!
このザイアンス効果を勉強に活用することで、記憶定着率を上げることが可能です。この効果は「繰り返し接触することで、親近感や好意、理解度が高まる」という心理学の理論ですが、勉強にも応用できます。以下で、具体的な方法を詳しくご紹介します。
活用方法
1. 毎日少しずつ同じ内容に触れる
具体例:日々の復習を習慣化
- 勉強した内容を24時間以内に復習することで、記憶の忘却を防ぎます。さらに、1週間後や1か月後に再度見直すことで、長期記憶に移行します。
- 例:
1日目に学んだ内容 → 2日目と7日目に復習
2日目に学んだ内容 → 3日目と8日目に復習
ポイント
- 復習の時間は短くても大丈夫です。10~15分程度、重要なポイントを見直すだけでも効果的です。
- 記憶に馴染ませるために、隙間時間(通勤中や休憩中)を活用するのもおすすめです。
2. 同じ教材を繰り返し使う
具体例:テキストや問題集の反復使用
- 新しい教材を次々と買うのではなく、1つのテキストや問題集を何度も繰り返し解くことが記憶定着の鍵です。
- 1回目: 全範囲をざっと通読
- 2回目: 重要ポイントを重点的に読み、理解を深める
- 3回目: 問題を解きながら知識をアウトプット
- 4回目以降: 苦手箇所を集中して復習
ポイント
- 同じ教材に繰り返し触れることで、内容に「親しみ」を持ち、理解度が深まります。
- 反復の過程で、「ここは覚えた」という達成感を得ることもモチベーションにつながります。
3. 視覚や聴覚を刺激して学習効果を高める
具体例:同じ内容を複数の形式で学ぶ
- 同じテーマを複数の方法で学ぶと、記憶が強化されます。
- 例:
- テキストを読む → 音声で解説を聞く → 図表で学ぶ
- 同じ内容を問題集で解いて確認する
ポイント
- 目や耳を使うことで、学習の幅が広がり、飽きずに続けやすくなります。
- 音読や動画視聴など、感覚を組み合わせるとさらに効果的です。
4. 過去問や問題集を繰り返す
具体例:間違えた問題を徹底復習
- 過去問や問題集を何度も解くことで、出題傾向をつかむとともに、知識を定着させられます。
- おすすめのやり方:
- 1回目は全問解き、間違えた問題をマーク
- 2回目以降は、マークした問題だけを重点的に復習
- 数回繰り返すうちに、マークした問題が減っていくのを実感できます。
ポイント
- 「間違えた理由」をノートに書き出すと、記憶に残りやすいです。
- 間違いを振り返ることで、次回同じミスをしなくなります。
5. 短時間×高頻度の学習を意識する
具体例:1日5~10分の反復
- 短時間でも、毎日勉強を続けることが重要です。長時間の学習よりも、5~10分の短時間復習を何度も繰り返す方が効果的です。
- 例:
朝食後に5分復習 → 昼休みに10分学習 → 夜に15分復習
ポイント
- 短時間学習の方が集中力を維持しやすく、続けやすいです。
- 習慣化しやすいため、忘れにくい学習スタイルになります。
私が使ったおすすめの参考書と教材
参考書
- 『社会福祉士国家試験のためのレビューブック』
→ 過去10年分の出題傾向が詳しく解説されています。
問題集
- 『社会福祉士国家試験過去問解説集』
→ 隙間時間に手軽に解けるのでおすすめです。
アプリ
- 社会福祉士解説と模試付き
→ 隙間時間に学ぶのに役立ちます。
まとめ

・計画を立てよう
しかし社会福祉士国家試験の範囲は非常に広く、すべてを完璧に網羅するのは難しいです。19科目ある上に、絶対に1科目一問以上正解しないといけません。そこでまずは、「どの分野をどの程度学習するか」を簡単に計画し、効率的に知識を身につけよう。
・やるべきは過去問の繰り返し
インプットを中心に参考書や、教科書を読むのではなく、ひとまず過去問を解いてみよう!!大体、一つの過去問を4〜5週程度するイメージでやっていくと良いと思います。何ども解いて、選択肢全て解説できるくらいを目標に仕上げましょう!
・単純接触効果で「親しみ」を学習に活用しよう!
単純接触効果を意識した学習法は、「継続」と「繰り返し」がポイントです。
毎日少しずつ同じ内容に触れることで、自然と記憶が定着し、試験勉強が効率的に進むようになります。「できることからコツコツと」を意識して、無理なく楽しく勉強を続けていきましょう!
・最後に
試験勉強は確かに辛いですが、合格したときの達成感は何にも代えがたいものです。私自身も途中で挫けそうになりましたが、計画的に勉強を続けた結果、見事合格することができました。皆さんも自分を信じて、一歩ずつ進んでください。皆様のご健闘を心よりお祈りしております。
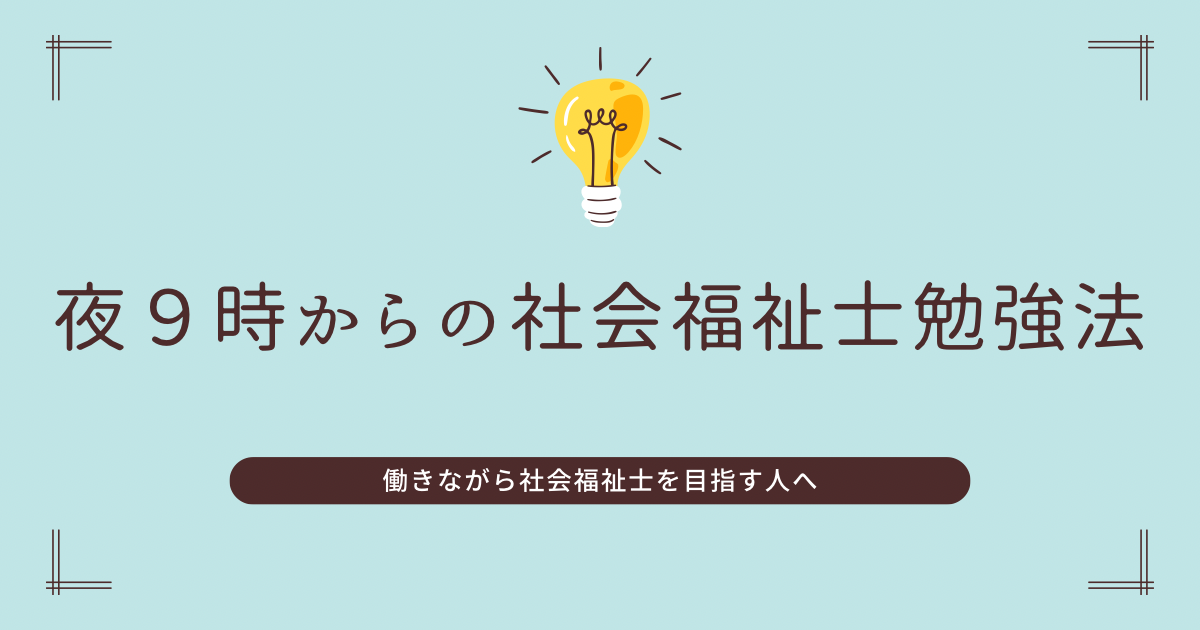
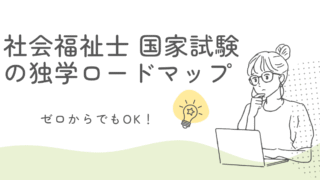
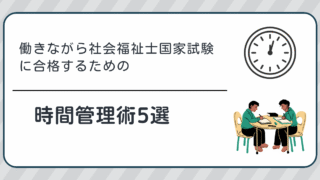
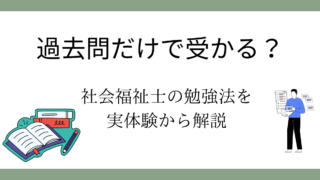

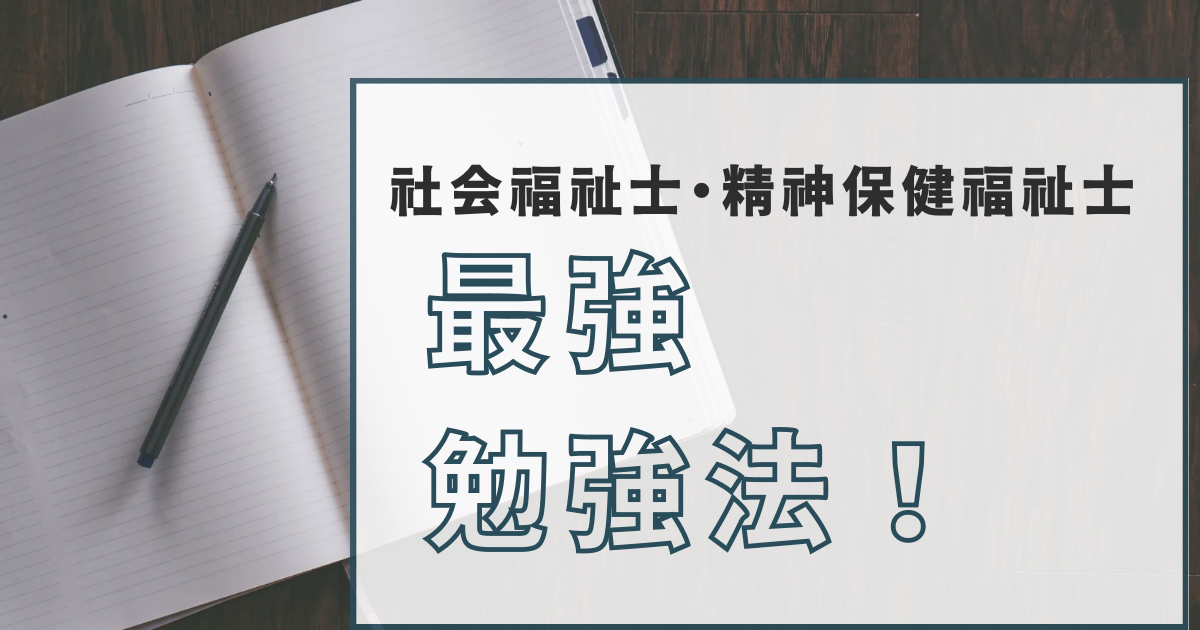
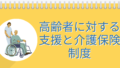
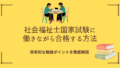
コメント